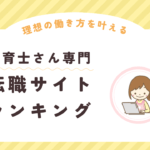こんにちは。保育士ライターのかのんです。
「いま、これがやりたい!」「これからこれがやってみたい!」「こんなふうにやってみたい!」こどもたちは、いつも真っ直ぐ。ド直球。
”今やりたくない”という想いの見方を変えると、”他にやりたいことがある”のかもしれませんよね。
実際の現場では、1日の流れがスケジュールとして決まっていることや、集団保育を行う中で、1人の子に時間を費やすことが難しい…なんていうこともあるかと思います。
私も幼稚園教諭時代、1日のスケジュールや人手の足りなさに、「もっと寄り添いたいのに…!」と頭を抱えることがありました…m(_ _)m
今回は、こどもたちの「やりたい!」という気持ちをより実現するためには、どのような方法があるのか、みなさんと考えていきたいと思います…!
目次
保育園・幼稚園1日のスケジュール(現場での実態)
現役保育士に聞いた!1日の流れ
保育園(1歳児)
9:00 おむつチェック
9:15 おやつ(牛乳)飲み終えた子から自由遊び
9:45 晴れの日は戸外遊び/ 雨の日はマット遊びか風船遊び
11:00 廊下階段探索
11:05 着替え
11:15 給食 食べ終えた子から午睡
(12:00には全員午睡)
14:45 起きた子からオムツ替え
15:00 おやつ 終えた子から自由遊び
保育園(3歳児)
10:00 主活動
11:45 お昼ご飯
12:30 午睡
15:00 おやつ
15:30 活動/自由遊び/散歩
幼稚園(5歳児)
9:00室内遊び
10:00 朝の会
10:20 戸外遊び
11:00 主活動
12:00 給食
13:00 着替え/ 帰り支度/
→室内遊び
15:00 降園
※スケジュールはあくまで一例です。施設の数だけ方針があり、一日の流れも異なります◎
排泄の促し、午睡チェックなど、活動の合間や生活、一つひとつを掘り下げて計画を練っている現場です。
現場の保育士・幼稚園教諭の声や想い
- 職員の配置により、他学年と合同保育となる
- 園が小さく、ホールがない
- 雨の日は、遊び場所が、廊下や階段になることがある
- 主体性保育の、保育者同士の認識がしきれていないことがある
- 幼児は、気持ちを受け入れながらも、メリハリをつけることが大切だと感じる
- バス通園のため、活動時間は異なる。
- 幼稚園は、基本一斉活動。寄り添いたいと思う子がいた場合も、保育者の人数的に厳しい時がある

「やりたい!」という気持ちをより実現できるようにするためには
このことを考える前に、まず思うことは、
日々の生活の過剰な制限により、経験できる場が減少していることから、やりたい!という気持ちになるものとの、出会い自体が減ってきている。ということ。
まずは、たくさんの経験ができる場を作ること。
好きなこと、やりたいことを見つけること。
好きになった物事に夢中になることで、自分自身を好きになり、自己肯定感も育まれていきますよね。

あれやこれやと言い合い、ルールやコミュニケーションを学び、次はこうしてみたい!という気持ちで溢れていたように思います。
園や学校などの施設以外にも、子どもたちの居場所を作る
今まで「やりたい!」と意欲で溢れていた子が、「言ってもどうせできないから。ダメって言われるから。言葉にしなければ、自分の心の中だけでおさまるから」と話してくれました。
しかし、イベントに参加した後、少し前の自分を思い出したように、ポツリとこう言ったんです。
「こんな大人たちに出会って、自分の意志をもっと持っていいんだなって思えた。」
「日常を忘れられた。」「わたしは、ここが好き。」
今、本当の想いを心にしまい、我慢している子が多いのではないかと感じます。
子どもたちが1日の中で長く過ごす集団生活だからこそ、難しいことがあり、子どもたちの制限が多くなってしまっている現状。
施設を否定しているわけではなく、施設だけではない場所での、新たな出会いや経験から得られるものも、多いのではないかと思います…!
子どもたちが、ありのままでいることのできる場所。
今の時代、今だからこそ、そのような場所も必要。

(撮影:フォトグラファー yu-min)
子どもたちの声に耳と心を傾け、何が必要なのか考えていけると良いですね^^

本当はこうしたいけど、組織的に難しい…
そのように悩まれている先生方もたくさんいらっしゃいますよね。
施設の人手を増やす
子どもたちを見る目、必要な時に差し伸べる手、様々な人とのコミュニケーションは、少ないより多い方が良い。
定められている職員配置人数を満たしていても、現場での、「本当はもっと寄り添いたいけど、そうすると活動が進まない…」「日常生活を送ることができても、もう一人いてくれたらもう少し一緒にいることができるのに…」
という想いは、人手が増えれば、現状より良い方向に進んでいく可能性があります。
だからと言って、保育や教育現場の人手不足問題には様々な背景があり、「明日から新しく1名に入っていただきましょう!」と人手が増えるわけではないですよね…。

社会に想いを伝えていく
1番勇気が必要で、1番難しい部分だと捉える方が多いかもしれません。わたしもその一人…(汗)
不満として伝えることも、自己表現の一つであり大事なことですが、
”こうすれば、働きやすい”
”こうすれば、子どもたちの意見が尊重される”
具体例を挙げ、お互いに歩み寄れるよう対話をしながら、まずは身近な人と話してみる。
同じ想いや考えの方と、少しずつ、少しずつ輪を広げていく。同時に、自分の考えと反対である方の考えを知ることも、より良い方法を見つけていく一歩かもしれません。
言葉にしていかないと何も変わらない。言い換えると、言葉にしていくと、少しずつかもしれませんが、良い方向へ進みます^^

最後に
今回、書かせていただいたことが全てではなく、正解不正解があることではない。そう感じています。
もちろん、何かを、否定をしているわけでもありません^^
これからを生きていくこどもたちに、ただただ思うことは、
自分のことが好きになり、楽しい!と思って生きていってほしい。
やってみたいと思うことには挑戦をして、失敗をして、考えて、人を頼り、頼られ、生きていく力を身につけていってほしい。

(カメラ、写真提供:阿曾琴美)
こうなってほしいなんて押し付けがましいかもしれません。
だけどね、やっぱり思うんです。
やりたい!と思って経験ができた先に、その子の可能性が広がっているかもしれない。
その可能性を潰したくはないと^^
大人である私たちも、自分自身がどうありたいか、こどもたちと過ごしていく中で、どのような自分でありたいか。
日々忘れず考えていきたいと思っています^^
たとえ、その瞬間に、目の前の子のやりたい気持ちを実現できなくても、その瞬間の気持ちを受け止めたり、共感できる心の隙間は開けておきたいですね♡
-
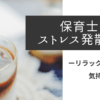
-
保育士のストレス発散方法ーリラックス方法4つと気持ちの保ち方ー
こんにちは!保育×環境について発信しているかのんです。 さあ!出会いがたくさんの4月がやってきました。新年度のスタートですね。3月を終えて、 ...