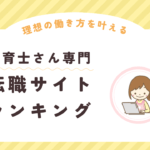こんにちは!ぽっくる先生(@2525pokkuru)です。
2019年5月11日、保育コミュニティ#HUGと、議論メシという議論コミュニティのコラボイベントが開催されました。
発足して6か月目になる#HUGですが、他コミュニティとのコラボイベントは初めて。
しかもその初めてのイベント内容が、保育をテーマにした議論…!
議論…!!?!
保育の世界で働いていると、他者と何かテーマを設けて話し合うという機会が少ないのではないでしょうか。
普段は0~5歳児と会話をしているので、使う言葉も雰囲気もまったく異なりますよね…(笑)
というわけで、私たち保育メンバー一同はドキドキしながらイベント当日を迎えました。
#HUG×議論メシのディスカッションイベント、一体どのような流れで何を話したのかご紹介します!
スポンサーリンク
目次
議論メシとは
「議論メシ」は多彩なメンバーがティスカッションでつながる共創コミュニティ。
議論でうまれる「つながり」と「アイデア」で仕事や暮らしを面白くする、というビジョンのもと運営されているコミュニティです。

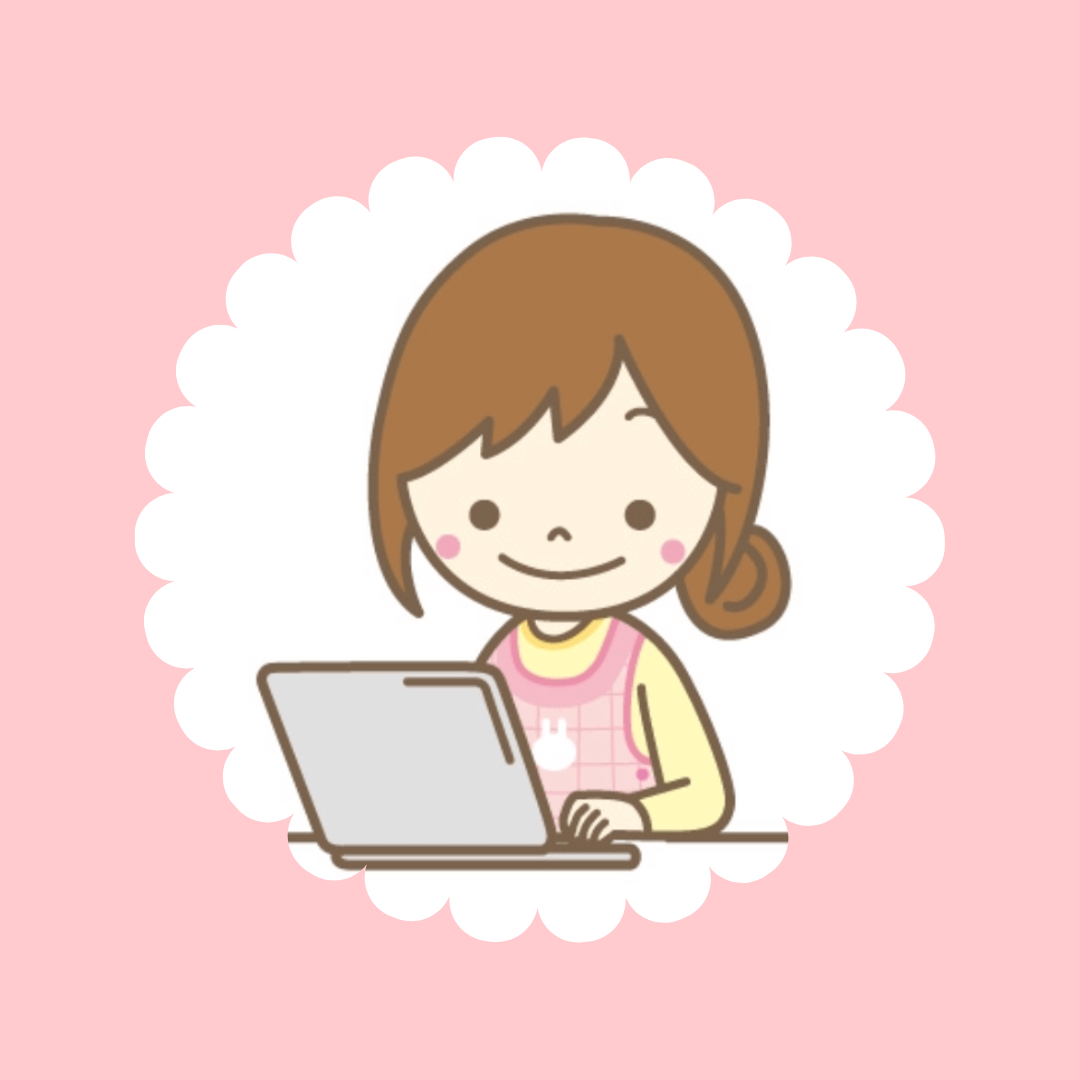
議論メシの詳細はこちら。
当日の流れ
イベントは都内の会場にて2時間。HUGメンバー6名、議論メシメンバー6名。半々ずつ2グループに分かれて進めていきました。
自己紹介
各グループ1人1分の自己紹介。名前と、今までの仕事歴、現在取り組んでいること、コミュニティに参加したきっかけ、趣味など、自由に話しました!
背景説明
イベント主催のHUGメンバーより、保育業界の背景説明をしていただきました。簡単に内容をご紹介いたします。
保育士不足
- 有効求人倍率は2倍(東京では5倍)
- 潜在保育士の増加(約80万人)
待遇・労働環境
- 平均年齢34.8歳、平均勤続年数7.6年、平均賃金21万6千円(中央値ではない)
- 労働環境改善要望の上位
①給与・賞与等の改善(59%)②職員数の増員(40%)③事務・雑務の軽減(34.9%)④未消化休暇の改善(31.5%) - 待機児童解消のため、東京都は4万4千円保育士の月給に上乗せ
保育士業務の難しさ
- 月齢や年齢ごとに異なる対応
- 個人単位での保育内容の工夫、継続した改善
- 一人あたりが担当する子どもの多さ(配置基準)
- 増え続けるルール、各方面とのコミュニケーション、雑務・事務時間の多さ
- 命を預かる重責
社会的背景の影響
〈待機児童問題〉
- H30に初めて待機児童数が前年比減を達成(認定こども園増設や、保育所利用定員の増加によるパッチ的対応)
- 政府は当初2017年までに待機児童を解消するプラン→現在の目標は2020年末
(子育て安心プラン政策/2022年までに女性就業率80%に対応できる受け皿の確保を目指す)
保育士に対するイメージ
「子どもと遊んでいるだけ」と認識されることも
→実際は専門性が高く、責任も重い仕事
- 指導計画の作成、実行
- 発達状況・季節性・社会性など考慮した上で保育計画を立て、子ども一人ひとりの成長を促す
- 事故やケガと隣り合わせ。最悪の場合、命にかかわることも
- 業務量が多く、持ち帰りや休日仕事が多い
ディスカッション
以上の背景を踏まえ、HUGメンバーからディスカッションしたいテーマを募りました。
〈議論テーマ〉
- 保育士の価値を向上するにはどうすればいいか
- 保育業界以外の方から見て、課題や改善できそうなポイント。してくれると助かること。
ディスカッションの目的は、正しい・間違っている、解決策を見つけることではなく、様々な意見を吸収したり、視野を広げるのが目的です。
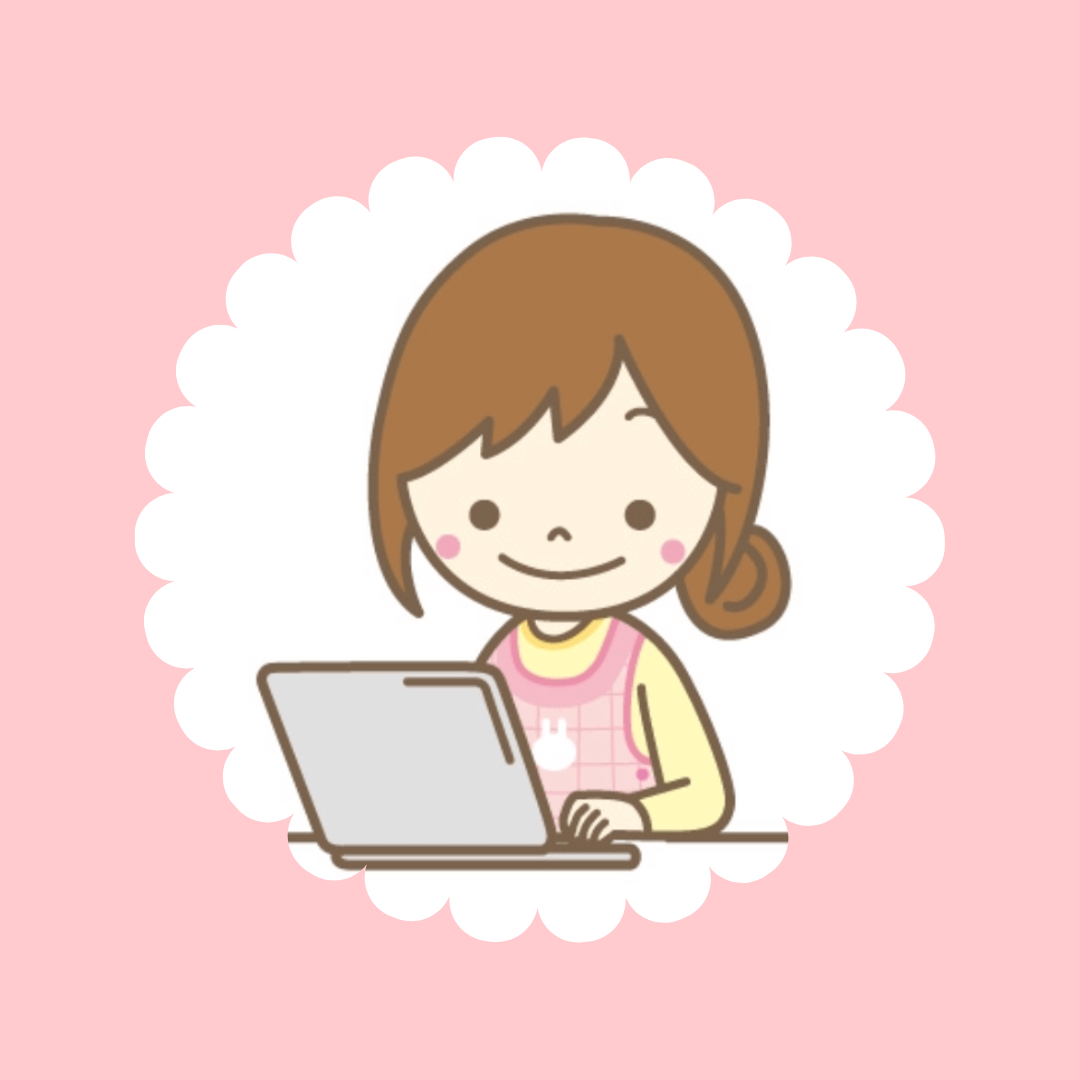
保育士の価値向上について
アニメ業界の話
日本のアニメ業界は現在改善が進んでいる。人が減っていて改善せざるを得ない状況(低予算で制作するなら海外に仕事を流せるため)
→保育業界は旗振りする人がいない?低賃金でも人がいなくならなければ改善されにくい。今は保育士不足で改善しやすい状況にあるのでは?
・保育士は自分たちの環境を改善したいと考えているが、根底に「福祉」という考えがあり、目の前の子どもたちを犠牲にできないと考える人が多い。
・「お金じゃなく子どものために働きたい」という思いがあるゆえに悪循環に陥っている部分もある。
保育園の収益構造
保育士の給与は保育料から出ているが、保育士に払う金額(人件費に何%割り振るか)というのは各園によって異なる。
保育士不足解消のため、最近は自治体から別途補助金が出ているところも多いが、現場の保育士に還元されているものとされていないものがある。
→これだけ保育士不足が深刻なのに、なぜ保育士に還元しない園が多いのか?
→そもそも保育士自身が収益構造を理解していないから変えられないのでは?
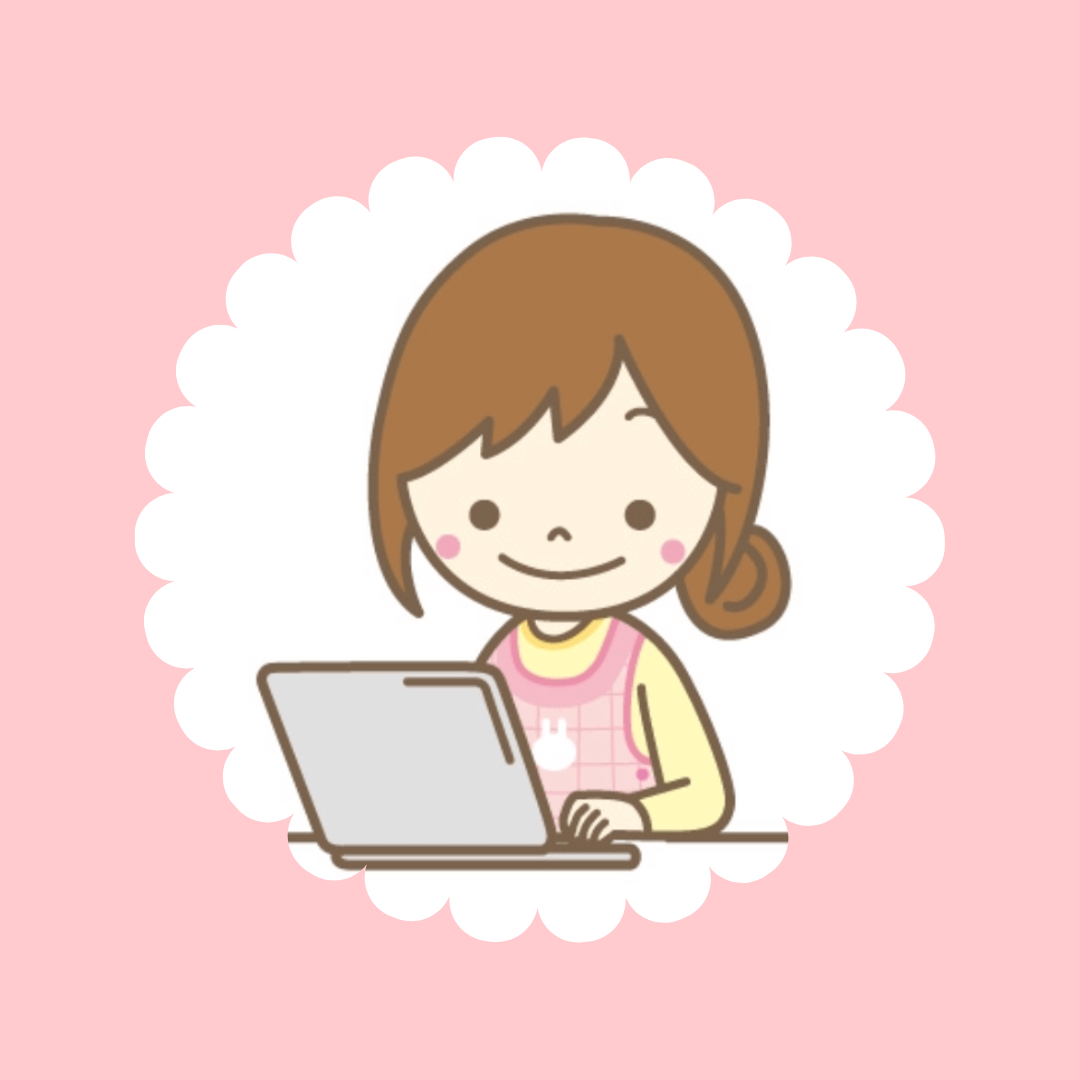
〈対策として〉
・世間や国に保育士の現状を発信し、保育士の給与を上げる流れに持っていく
・訴えるべきところに訴えないと構造は変わらない
・給与が高い園=働きたい保育園ではない。業務量や人員的余裕、保育内容も保育士は重視している
資格あり・なしで担当できる仕事の違い
最近、保育士資格がない人を活用する動きが出てきているが、資格がある人とない人、どこで仕事内容に違いが出てくるのか?
〈保育士しかできない仕事〉
・子どもの人数に対しての保育士配置人数を満たす必要がある
・書類作成業務(子どもの育ちの記録、保育計画の作成)
→その他の業務をサポートしてくれる人を活用すれば業務の改善はできるはず
→そもそも保育士の配置人数がギリギリなので、サポートできる量も限られているという問題点もあり
経営知識と保育知識
〈美容業界にいた方の話から〉
・美容室の経営…美容について全く知識のない経営者の店がとても上手くいっていた。その理由は、経営者は経営に専念し、現場のことは美容師の意見を何よりも尊重していたから。
→保育業界ではどうか?
・保育知識がない経営者だと、現場の保育士と意見がすれ違って対立してしまう例もある。
・保育を理論的に説明できず、経験や自分の保育観だけで成り立たせてしまっている園長もいる。
保育士が保育の仕事の専門性を言語化して周囲に伝えていく努力も必要である。
保育の仕事に価値をつけるなら?
HUGメンバーが保育士を対象に「自分の仕事を時給換算するならいくら?(上限なし)」というアンケートをとったところ、1200円~1300円と答える保育士が多かった。
・それで生活できるのかを改めて質問すると、言葉に詰まる保育士もいた
・保育士自身が保育の仕事の価値を低く見ている?
・他の業種の相場観などをわかっていない
・「●●をしたら○○円」と、仕事に対するお金の見える化をしてもいいかもしれない→無駄がなくなる
・業務時間内で何をしているのかが伝わらない、説明できないと、経営者としてもお金を払いにくい
業務内容の見直し
〈参加者の経験談から〉
・手作りの壁面装飾、子どもたちへのプレゼント、メダルなどの景品は時間をかけてつくる必要がある?印刷したものでもいいのでは?
・書類は手書きである必要があるか?
→保育士の中で「手作り(手書き)だから愛情がある」「時間をかけたものほど良い」という感覚が根強いのも事実
〈オーストラリアの保育園では…〉
HUGメンバーがオーストラリアの保育園で見た光景
・子どもたちに「りんご」の見本を見せるとき、ちらしを切ったものを見せていたし、YouTubeなども普通に見せていた
・絵本はCDが読み聞かせ。先生はページをめくる役割だが、聞いていないため音読とページが合わないことも(笑)
→日本の保育士は質が高いことをしているのに、それを自覚できていないことも問題。
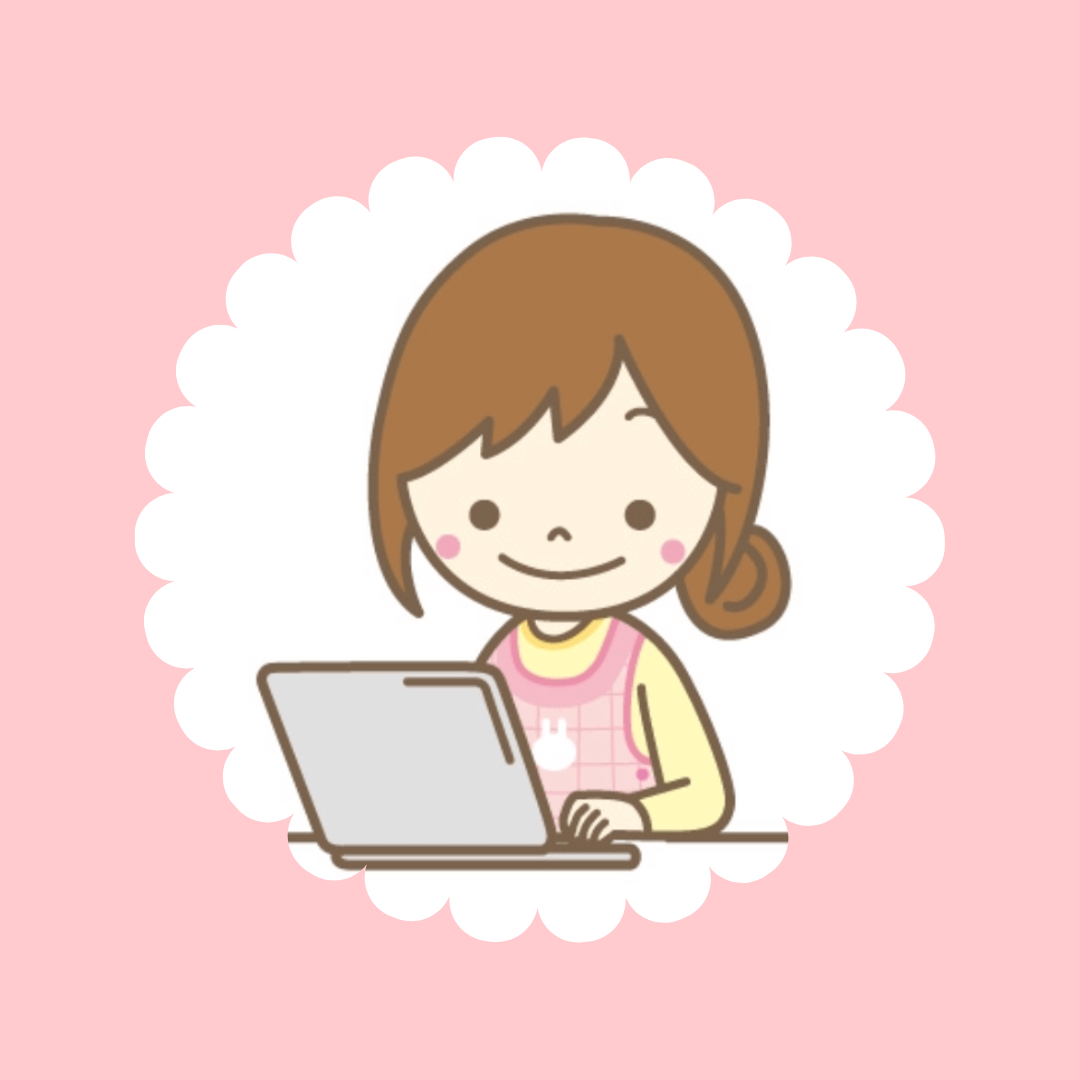
保育業界の課題、改善ポイント
”保育”の枠を壊して、ビジネス視点で考えていく
(もちろん、安心安全・専門知識を持ったうえで預かるという部分は念頭に置いて)
⇓
〈なぜそう考えるか〉
保育という枠にとらわれすぎているのではないか。
IT、コンサル、などと同等に保育という立ち位置を持ってくる。
①ビジネスモデルを作り上げる
保育園が今後無償化になれば、3歳児以上の家庭は今まで園に払っていたお金が浮く。そこに視点を置いて、+αを支払っても良い仕組みを考える。
EX)
飛行機会社のような仕組み作り
LCCのように安い飛行機は、荷物の追加、座席指定などオプション料金として追加するスタイル。JALやANAなど大手などはそもそもの値段が高いという差別化をしている。
LCCの飛行機は多少不満があっても、”安いから”という納得が出来る。
↓
保育園の場合…
保育士の専門性や子どもと関わる時間などに労力をかけられるよう、業務改善。
・ICT化の導入(午睡、登降園管理など。しかし、現場のICT化へのアレルギーもあり)
・連絡帳などをオプション化(文章が必要な時は+OO円)など
・子どもに手を掛けられない要因となるもの、専門的知識が必要のない作業の廃止
EX)
保育園のスペースが空いている場所・時間帯を他の団体や企業などに貸す
レンタルスペースのイメージ。
⇒管轄の問題で、現状は難しい…?
②保育者の言語化
保育園以外で活躍できる場所の拡大。専門性が必要とされる場所は多くある。
・子役との関わり⇒広告撮りなどの現場で専門性が役立つ
・主婦向けのイベント、動画(子どもとのかかわり方、遊び方)
・YouTubeなどに出てくる広告などで保育業界verを作り、保育の仕事を知ってもらう。(どんな業務をしているのか知らない人が多い、ポジティブなイメージを付ける)
*保育の専門性を言語化できていない人も多いので、そこから見直す必要あり。
③企業を参入させる
話の中では、例えば楽天など…と大手企業が話にあがったが、どんな企業や業種が良いかまでは深く掘れず。
【まとめ】
- 「行政」「経営」「現場」「保護者」「子ども」この中でどこにアプローチをしていくか。
- 経営、保護者、現場へのアプローチが、結果”子ども”に繋がる。
- 専門性をもっと生かすべきで、子どもたちと向き合う時間を第一に考える仕組みに変えていく必要があるのではないか。
まとめと感想
保育者同士ではなかなか出ない意見や疑問を聞くことができた今回のディスカッション。
話したからすぐに何かが解決するわけではありませんが、解決のタネとなるような考えがたくさん生まれました。
議論メシメンバーより、
*短い時間だったけど、保育について知らないことが8割だった!もっと専門性を発信していけば、可能性があるのでは?
とのお言葉をいただきました。
私が感じたことは、普段保育者同士で話をしていると、保育の知識があって当たり前という中で会話をしているんですよね。
「世間が保育士の価値をわかっていない!」という声もよく聞くけれど、じゃあ私たちは知ってもらう努力をしているのか?と考えると…どうでしょうか。
同じく私たちも、他の職業について知っているのかと問われると…そこまで知らないですよね。
保育士の賃金問題は国レベルで改正していかないと解決できない部分も多いですが、保育士の価値(専門性)を発信していくことは、今すぐにでもできるかもしれません。
#HUGの中でも、保育業界をよくしよう!と、様々なプロジェクトや話し合いが行われています。
今回出たことをヒントに、さらなる取り組みに繋げていきたいと思います!
〈保育コミュニティ#HUGの詳細はこちら〉
随時メンバー募集しております*
-
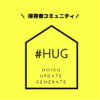
-
保育オンラインコミュニティ#HUG【入会案内】
2018年12月に始動した保育コミュニティ「#HUG」。 保育コミュニティって何?? どうやって参加するの?? 参加するメリットは?? など ...
〈イベント終了後も盛り上がるメンバーの様子〉